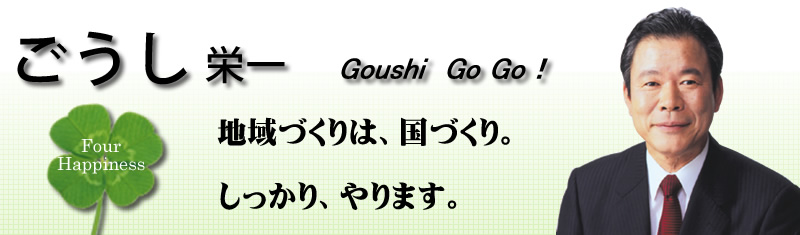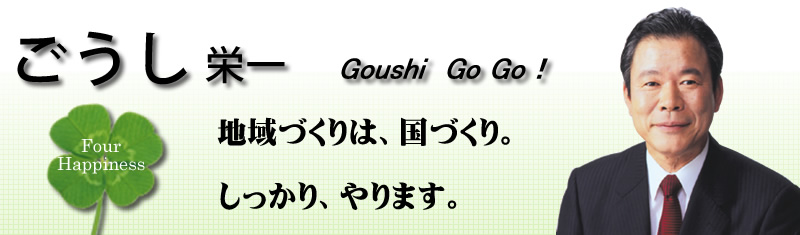|
 |
|
 平成25年 一般質問項目 平成25年 一般質問項目 |
|
2月議会 |
6月議会 |
9月議会 |
11月議会 |
|
|
| |
○2月定例県議会 |
| |
子育て支援について |
| |
「子育ては、楽しい。」、そう子育て中のお母さん方が思える環境を整えていくことが、子育て支援の施策の大事な柱であると考えます。
子育て支援は、少子化対策でもなければ、雇用対策でもありません。子育て支援は、子育てのより良い環境を整えていくことそのこと自体が目的であり、その目的に沿った施策が自ずと少子化対策ともなり、雇用環境の改善にもなるものと考えます。
昨年2月17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」において、社会保障改革の第一の柱に、未来への投資ということで(子ども・子育て支援)の強化が位置づけられたことは、画期的でした。社会保障と言えば、これまで医療・介護・年金のことでありましたが、新たに「子ども・子育て支援」が、財源的裏付けを持って推進すべき最優先の国の社会保障政策の柱として加えられたからです。
そうした関連の中で子育て三法が成立し、子ども・子育て支援が国の社会保障政策の一環として、より拡充される方向で取り組まれることになったことは歓迎すべきことであり、評価するものであります。
子育て三法の主なポイントは三つあります。
その第一は、認定こども園制度の改善です。
幼稚園の機能と保育園の機能とを併せ持つ認定こども園は、認可や指導監督等の所管が、幼稚園機能は文科省、保育園機能は厚労省と二元管理になっていたのを、内閣府が統一的に所管し、文科省や厚労省は必要な連携、総合調整を通して関与するという仕組みに改善されました。また、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けが明確にされました。
第二は、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設です。
このことにより、認定こども園・幼稚園・保育所の各事業者への運営費補助は、原則内閣府から給付されることになりました。また、現在認可を受けていない小規模な保育施設に対しても、市町村が地域型保育の必要性を判断したうえで、新たに市町村が定める認可基準を満たしている場合は、運営費補助が行なわれることになりました。
第三は、地域の子ども・子育て支援の充実です。
子育て中のお母さん方が、親子ともども自由に集い交流でき、また子育ての相談などもできる場所を、地域地域に開設していく地域子育て支援拠点事業等が、市町村が行なう地域子ども・子育て支援事業として明記されました。
こうした子育て支援の施策には、二つの方向があると思われます。いずれも、子どもを産み育てやすい地域社会の形成を目指すという点では共通ですが、一つは、地域社会自体が提供する保育の量と、幼児期の学校教育や保育の質の向上といった保育機能を拡充する方向です。もう一つは、お母さんの子育てを支える地域環境を整えていく方向です。
先程の、子育て三法のポイント第一と第二は、前者であり、第三は、後者であると言えますが、私が、ここで強調したいことは、地域社会自体の保育提供体制の拡充も、お母さんの子育てを支える地域環境を整えていくことも、同等に大事であるということであります。
そういう観点から、今回はお母さんの子育てを支える地域環境を整えていくことにつき質問を行うものであります。
尚、お母さんの子育てと申しますと、子どもを育てるのはお母さんだけではない、父子家庭もあるぞとの指摘を受けるかもしれませんが、ここではお母さんという言葉は、お母さんの役割を果たす人という意味で使っているというようにご理解いただきたいと思います。
さて、ご案内のように我が国では、子供たちは3歳になるとほとんどが保育園か幼稚園に入園いたしますが、0歳から3歳未満の子供たちの場合、保育園等にお世話になるのは2〜3割で、7〜8割の子供たちは家庭で主に母親が育てています。
私は先程、お母さんの子育てを支える地域環境を整えることの大事さを強調しましたが、それは、ことに7~8割と見られている3歳未満の未就園児のお母さん方の子育てを支える環境を整えることの大事さであると言えます。
昔は、そういうお母さんの子育てを、家族や隣近所のつながりのなかで支える環境が普通に存在していたように思われます。それが、今日の時代、核家族化が進行し地域における人と人とのつながりも希薄化の傾向にあることから、子育て中のお母さん方を支える地域環境を意識的に創り出し整えていく取り組みが求められています。
こうした要請に応える事業として今日推進されているのが、「地域子育て支援拠点事業」であります。
未就園児を持つ家庭への支援として、先ず始められたのは平成7年からスタートした保育所の機能を活用し子育てに関する専門的な相談や交流を図る「地域子育て支援センター事業」でした。次いで、平成14年から空き施設や空き店舗等を活用し身近な場所で気軽に集える環境整備を目的とした「つどいの広場事業」が始まり併せ展開されることになりました。この両事業が、平成19年に再編統合されて「地域子育て支援拠点事業」として推進されることになり、今日に至っております。平成21年には児童福祉法が改正されて、この事業の法律上の位置づけが明確にされました。そして、平成22年に策定された「子ども・子育てビジョン」では、平成26年までに全国1万カ所の子育て支援拠点を整備する目標が示されているところであります。
では、山口県における「地域子育て支援拠点事業」の取組み状況は如何でしょうか。平成25年1月現在、本県では139カ所の地域子育て支援拠点があります。平成26年度目標数が150カ所でありますので、ほぼ目標達成が視野に入っており、高い水準で本県の子育て支援拠点の設置が進んでいることが分かります。ただ、この設置状況を仔細に見ていきますと、より優れた子育て支援の環境整備に向けて、課題も明らかになってまいります。山本知事は、昨年10月に発刊された山口県の「平成24年度子育て文化創造白書」において、「子育て環境日本一の県づくりの実現を目指す」旨、表明されています。
つきましては、知事表明の「子育て環境日本一の県づくり」に向けて、子育て支援の地域環境が、より一層豊かに整い充実していくことを願い、以下数点お伺いいたします。
お尋ねの第一は、子育て支援の施策推進の基本方針についてであります。
子育て支援が社会保障政策の中に位置づけられ、子育て三法が成立して、国・都道府県・市町村の役割も明確にされ、云わば国を挙げて子育て支援の政策がこれから推進されようとしています。そうした中、本県は今後どういう基本方針のもと、この子育て支援の施策を推進し役割を果たしていくお考えなのか、先ずお伺いいたします。
お尋ねの第二は、子育て支援拠点の設置推進についてであります。
先ず第一点目として、先程子育て支援の施策として、地域社会自体の保育提供体制を拡充していく取り組みも、お母さんの子育てを支える地域環境を整えていく取り組みも、同等に大事である旨申し上げましたが、こうした子育て支援の施策についての基本認識につきましてご所見をお伺いいたします。
次に第二点目として、「つどいの広場型」子育て支援拠点の設置推進についてであります。
「同世代のお母さん方と、話ができることでストレスも解消する。」
「主人は、仕事でほとんど家にいない。子どもと二人きりの生活でストレスがたまっていた。ストレスがピークの頃、ここを知った。ここでは、スタッフが子どもを見てくれて、少し離れて見ることができ、ゆっくりできる。」
「何で、こんな思いをしなくてはならない、と一人でかかえこまなくてすむ。自分だけではない、とお母さん同士共有し合えて、気持ちが楽になる。」
「いろいろと先輩ママの話が聞けて育児の参考になる。」
「二人子どもがいるが、三人でいけるところが少ない。ここに来たら安心。家で三人で居るより、ここに来た方が楽しめる。」
「我が家はアパート住まいで狭い。ここは、自分の家のような感じで過ごせる。子どもは子ども同士で遊べる。お互い息抜きができ、くつろげる。」
「ここがなかったら、どうやって過ごしているだろうか、と思う。」
以上は、山口市内にある「つどいの広場型」子育て支援拠点数カ所を訪ねて、そこに集うお母さん方から聞いた声の一端です。
「つどいの広場型」子育て支援拠点は、空き施設や空き店舗、空き家等を利用して子育て中のお母さんが親子ともども、自由に集い交流できる場所でして、子育て支援を目的とする地域組織やNPO法人等が運営主体となり、スタッフには、母子保健推進員や子育て経験豊かなお母さんのお母さん世代、また先輩ママ等がいることから、子育て相談にも応ずることができる、そういうところであります。
私は、そこに集うお母さん方の声を直接聞いて、こうした「つどいの広場型」子育て支援拠点の開設が、全県的にもっと推進されるべきではないかとの思いに至った次第であります。
地域子育て支援拠点は、支援センター型、つどいの広場型、児童館型の3タイプありまして、最も多いのが「支援センター型」で主に保育園に併設されています。先に本県の子育て支援拠点の総数は139と申しましたが、そのうちの121カ所は、この「支援センター型」で、「つどいの広場型」は、グッと減りまして現在17カ所であります。而も、その17カ所のうち9カ所は山口市であります。尚、児童館型は、全県で1カ所です。
私は先程、本県の子育て支援の拠点整備の水準は高いものの、子細に見た場合課題があると申し上げましたが、その一つが、この「つどいの広場型」子育て支援拠点の増設です。
「支援センター型」拠点は、ほとんどが保育園併設で保育士が配置されます。よって、専門的な見地から子育て支援ができる点に特徴があります。一方、「つどいの広場型」拠点は、集いやすく地域や人との親しいつながりができる点に良さがあると思われます。
この二つのタイプの子育て支援拠点施設が、全県の地域地域に両方あってこそ、
山本知事が目指す「子育て環境日本一の山口県」が実現するのではないでしょうか。
そこでお尋ねです。本県は、地域子育て支援拠点事業における設置目標は、ほぼ達成の水準にありますが、その9割近くは「支援センター型」であることから、「つどいの広場型」子育て支援拠点の増設に、目標を定めて取り組むべきだと考えます。そして、「支援センター型」と「つどいの広場型」の両方の子育て支援拠点がある地域子育て環境を全県的に実現すべきであると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
次に第三点目は、地域子育て支援拠点事業への県負担についてであります。
子育て三法のひとつ「子ども・子育て支援法」は、その第65条から68条までの条文で、子育て支援事業の実施主体である市町村が、費用を支弁すべき事業と、その費用の国及び都道府県の負担について規定しています。
それによりますと、保育施設に係る施設型給付及び地域型保育給付については、国が2分の1、都道府県が4分の1の負担となっています。これは、従来の認可保育園への運営費補助の在り方を、小規模な保育を提供する施設にまで拡大して明文化した規定と言えます。
一方、地域子ども・子育て支援事業に係る費用の、国及び都道府県の負担については、「予算の範囲内で交付金を交付することができる。」と記されていて、どういう割合で国及び都道府県が負担するかが制度として担保されていません。
これでは、国の子育て支援の政策は、保育の提供体制の整備も子育て支援の環境整備も同等に大事であるとの基本認識を欠いているのではないかと言わざるを得ません。そうとは云え都道府県の裁量に委ねられたからには、本県においては同法第59条に列挙されている地域子ども・子育て支援事業のうち、特に第9号の地域子育て支援拠点事業については、子育て支援の地域環境整備を、保育提供体制の整備と同様に重要視する政策判断に基づき、費用の2分の1は国が負担すると見做し、4分の1を県負担とすることが望ましいと考えます。
「支援センター型」ないし「つどいの広場型」等の子育て支援拠点を運営する事業が、この地域子育て支援拠点事業でありまして、これまで事業費用の概ね半分相当が国からの交付金でまかなわれてきています。よって、この事業の費用を、国が2分の1負担することは事実上行なわれていて、後の半分は、実施主体の市町村が負担し、県負担はありませんでした。そこに、国の2分の1負担に加え、県の4分の1負担が行なわれるようになれば、県下の市町は、地域子育て支援拠点事業へ一層取り組みやすくなり、課題である「つどいの広場型」の子育て支援拠点の設置も全県的に進むのではないかと期待するものです。
そこでお尋ねです。子ども・子育て支援法で、都道府県は「予算の範囲内で交付金を交付することができる。」と規定されている地域子ども・子育て支援事業のうち、地域子育て支援拠点事業については、本県では費用の4分の1を負担するようにするのが望ましいと考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。
次に第四点目は、元気子育て支援センター推進事業についてであります。
元気子育て支援センター推進事業は、平成17年に創設された単県事業であります。
国が推進する地域子育て支援拠点事業は、市町村が保育園等の事業者に支給する事業費の半分相当が、子育て支援交付金で補助されることになっています。ただ、そのためには保育園等の事業者は、週に3日ないし5日以上開設すること、一日の開設時間が5時間以上であること、保育士等を1名ないし2名配置すること等の運営水準を満たすことが求められます。
こうした国が求める水準に応ずることが難しい過疎地域等の子育てニーズに対応するため、補助要件を緩和して子育て支援の拠点事業をやりやすくしたのが元気子育て支援センター推進事業でありまして、国の制度が行き届かない過疎地域等を、県事業でカバーしようとするものです。尚、県の事業費補助は2分の1であります。
実は、本県の支援センター型の地域子育て拠点数は、121カ所と申してきましたが、より正確に申しますと、その内40カ所は、この元気子育て支援センターでして、国の子育て支援交付金交付の対象になっている支援センターは81カ所であります。
この現在40カ所の元気子育て支援センターへの事業費補助は、平成17年度から21年度までは単県で、平成22年度と23年度は、国から交付されて県において造成した「山口県安心子ども基金」を活用して行なわれて来ました。
それが、今年度すなわち平成24年度から、この事業への補助がなされていません。当該事業にかかる国の「安心子ども基金」の予算措置がないようになったからです。
元々、この元気子育て支援センター推進事業は、県からの運営費補助を3年間と定めており、その補助期間で事業が軌道に乗り市町で継続されることを期待したものでありました。しかし、この事業への補助がなくなったことにより、事業実施が困難となり過疎地域等での子育て支援環境が後退することがあってはなりません。むしろ、過疎地域等だからこそ、子育て支援の環境をより充実していく取り組みが必要であることは言うまでもありません。
そこでお尋ねです。元気子育て支援センター推進事業への補助が今年度からなくなったことの影響をどう見ておられるのか、先ずお伺いいたします。
次に、子ども・子育て支援法では、保育提供の拡充ということで、地域の実情に応じてこれまで認可を受けていなかった小規模の保育園等も、保育ニーズ調査により必要性が認められれば、地域型保育ということで運営費補助をするようになりました。同様に、地域子育て支援拠点事業はバリエーションを増やして適用対象の事業を拡大し、本県が実施してきたような過疎地域等をカバーする元気子育て支援センター推進事業も包含できるものに改めるよう国に要望すべきであると考えます。ついては、このことにつきご所見をお伺いいたします。
また、そうした要望に国が応える措置をするまでの間、元気子育て支援センター推進事業への単県補助の再開を検討すべきであると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
|
| |
エネルギー政策と上関原発建設計画について |
| |
エネルギー政策と上関原発建設計画について端的にお伺いいたします。
第一は、山本知事は、我が国の今後のエネルギー政策は、どうあるべきとお考えなのかについてです。
知事選挙の時、山本知事は「3.11を体験した日本人にとって、脱原発依存はあたりまえの話です。」と、明言されました。
この考えは、今も変わっていないのかお伺いいたします。
第二は、原発依存を減らすという方向と上関原発についてです。
平成22年6月に策定された国のエネルギー基本計画は、54期ある原発を、さらに14基新設・増設して我が国の総発電量において原発が占める割合を、3割から5割に増やすというものでした。その新設・増設14基の原発の中に、上関原発2基が計画されていました。
このエネルギー計画は、3.11福島原発事故後、白紙に戻して見直すことになりましたが、これに取り組んだ民主党政権は、2030年代の原発ゼロの方針は示したもののエネルギー基本計画そのものの見直しまでには至りませんでした。
そして、昨年末の総選挙で自民党が勝利し第二次安倍政権が誕生しました。安倍総理は、「前政権が掲げた2030年代に原発稼働をゼロにするとの方針は、ゼロベースで見直す。」と国会で答弁しております。
ただ、自民党が総選挙の時、エネルギー政策については「原発依存は減らしていく。」という方針を公約しており、この方針は、安倍総理も言明しているところです。
そこで、私が指摘したいことがあります。それは、原発依存を減らしていく方向に、上関原発の建設はない、ということであります。
原発依存を減らすと言いながら、上関原発の建設を容認する政治家がいるとすれば、彼は真剣に、本気に原発依存を減らすことを考えていない、ただポーズとしてそう言っているだけで、有権者をごまかしていると言わざるを得ません。
新設・増設の計画がある14基の原発のうち、既に原子炉設置許可が下り、工事計画が認可され着工しているのが3基あります。それ以外の11基の中には、福島第一原発で増設予定だった7号基、8号基や、福島県浪江町・小高町に新設予定の1号基もあって、これらの建設はないと見れば、新設・増設の計画があるが未着工の原発は8基ということになります。この8基の中で、純然たる新設は上関原発の2基で、ほかの6基は全て増設であります。増設は、言うまでもなく既に原発が建設されているところに、新たに建設されることです。
このことから、私が申し上げたいことは、上関原発建設計画が、実施になれば、それは、我が国のエネルギー政策が、福島原発事故以前に戻ったに等しい、ということであります。私は、そういうことは断じてあってはならないと考えております。それは、多くの人達が犠牲になり、過酷な運命に追いやられ、我が国が存亡の淵に立たされた、3.11の大震災そして福島原発事故から、何の教訓も学んでいないに等しいと思われるからです。
私は、3.11の大震災とそれに伴う福島原発事故は、ある意味、我が国への天の警告であり、原発拡大路線からの転換を促すものであった、と受け止めております。
3.11大震災で2万名近くの人々が犠牲になりました。そして、福島原発事故では、東日本壊滅の一歩手前という戦後最大の危機的事態に直面しました。
そのような多大の犠牲を払い、深刻な危機に直面した体験から教訓を学び取り、よりよい日本を創っていくことが、今この国に生きている私たちの責務なのではないでしょうか。
上関原発の計画は、それが建設になるか中止になるかが、我が国のエネルギー政策が、原発依存を減らす方向に行くのかどうかの分岐点になるものと思われます。
福島原発事故を経験したことにより、将来原発をゼロにするかどうかはともかく、原発依存を減らす方向に進むことは、ほぼ日本国民の総意、コンセンサスになっていると見ております。
そこで、山本知事にお伺いいたします。
私は、国のエネルギー政策において原発依存を減らしていくことが、国民の総意であり、その方向に上関原発の建設はないと見ておりますが、このことにつき知事のご所見をお伺いいたします。
第三は、公有水面埋立免許の延長申請についてであります。
山本知事は、今議会で上関原発建設に係る公有水面埋立免許の延長申請についての判断は、1年間先送りする考えを表明されました。
要は、「国のエネルギー政策における上関原発の位置づけが不透明だから許可できない。」との考えから、「国のエネルギー政策における上関原発の位置づけが不透明だから判断できない。」との考えに変わり、「今後1年間の間に国のエネルギー政策における上関原発の位置づけも明確になるであろう。」との見通しで、判断の1年間先送りの表明となったものと見ております。
1年間判断先送りの理由は、そのような理解でいいのか、お伺いいたします。
また、そのことは、経済産業省が国の「エネルギー基本計画」の諮問機関として新たに総合資源エネルギー調査会総合部会15人の委員を決め、年内の基本計画策定を目指して、議論を再開することにしたことと関連があるのか、併せお伺いいたします。
第四は、県の基本的な考えについてであります。
県は、これまで上関原発建設計画に対しては、「国のエネルギー政策に協力する。」「地元上関町の政策選択を尊重する。」との考えに立って対応して来られました。そして、その考えは山本知事も同じであり、踏襲しておられます。
しかし、私達は3.11の原発事故から、原発建設問題は立地自治体だけの問題ではなく、広範な周辺自治体も含めた広域的問題であることを学びました。
ご案内のように、広域行政は県の役割であります。
そこでお尋ねです。上関原発建設計画については、「地元上関町の政策選択を尊重する。」との考えを踏まえた上で、「山口県全体の民意を代表する。」との立場に立って国に対して対応すべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。
|
| |
|
|
|
| |
○6月定例県議会 |
| |
産業政策について |
| |
政治は、理想と現実をつなぐ総合的な営みであります。理想なき現実論も現実を無視した理想論も共に政治たり得ません。理想と現実をつなぐ格闘こそ政治の本質であります。
私は、山本知事が官僚から政治家に身を転じられ、山口県知事として理想とするモデル地域の実現に向けて懸命に格闘しておられるお姿に、政治家としての苦悩と輝きの両方を見るものですが、目指しておられる方向は正しいと思っております。
どうか山本知事におかれては、御身を大事にしつつ所信を成し遂げられますよう心からエールを送ります。
私は前回の県議会の時、山本知事の政治家としての思いを簡潔にまとめた「皆さん、どうか力を貸して下さい」というタイトルの冊子のことに触れましたが、
今回は、その内容を少し紹介しようと思います。山本知事が理想として掲げ、その実現を目指しておられる方向を、議員同士お互いに知っておくことも意義あることかと思うからです。では、以下冊子からの引用です。
世界中どこの国でも、経済成長のけん引力となった2次産業、3次産業と農林漁業とのバランスをとって進まなければ、国民の暮らしが成り立たなくなる時代がやってきます。
江戸時代が、世界に類例のない高度農業社会だったという事実を学んだのは旧建設省で国土政策を担当するようになってからです。
当時としては、世界最大級の人口規模を誇る江戸の清潔さも彼ら(幕末に日本に来た西欧列強の軍人や外交官たち)にとって驚きでした。
玉川上水などの水供給施設と井戸などの取水施設を組み合わせた高度な上水システム。近隣の田園地帯からの生鮮食料品の供給と排泄物や生ごみなどの都市廃棄物の処理(肥料としての活用)を、
舟運を中心に一体的かつ合理的に取り扱う供給処理システム、これらの高度な都市システムは、暮らしの中で花や植物を愛する江戸市民の生活態度と相まって、
この時代の西ヨーロッパの都市の水準からは飛びぬけて美しく清潔な百万都市江戸の姿を西洋人に印象付けたのです。
私たちはもはや工業化以前の暮らしに戻ることはできません。経済の発展を目指して歩み続けなければなりません。問題となるのはその発展の中身です。環境問題の解決のために目指すべき方向は、自然と人との営みの調和です。
農林漁業と工業、商業のバランスです。田園と都市の共存です。この方向を目指すとき、江戸時代に我が国が実現した高度農業社会の在り方が大きな手がかりになると思うのです。
現在の世代だけでなく、子や孫の世代さらには末代までの幸せな暮らしを考えて今の生活を営む、持続可能性を正面に掲げた社会。
四季を通じて、自然の力を最大限活かして生産し、生産したものを大切に使うだけではなく、再利用、循環利用することで活かしきる社会。
商工業を営む都市と、農林漁業を営む田園がお互い補い合い支えあって共生する社会。
持続、循環、共生。この三つを大切にする社会を目指して進んでいくほかには、道はないと思うのです。
以上、紹介いたしましたことから、私たちは山本知事の念頭に常にある思いを推察することが出来ます。それは、将来の世代のために、よりよい地球環境を持続していくということと、
経済成長を続けて生活の向上を図っていくということが両立する地域社会モデルを、江戸時代の日本が実現した高度農業社会の在り方を手がかりに、
山口県において実現していこうということであります。そして、その地域社会モデルが目指す方向は、次の三つに要約されます。
1.自然と人の営みが調和している低炭素社会
2.自然、天然の力と生産物を最大限活用し生かす循環社会
3.農林漁業と工業、商業がバランスよく発展し共生する社会
こうした地域社会を本県において実現していこうという方向と、山本知事が最も力を入れておられる本県産業力強化の政策を、
どう繋げていくのかということが第一の質問の趣旨で、二点お伺いいたします。
今議会初日に、「やまぐち産業戦略推進計画」の中間案をお示しいただきました。これを見まして、私は、県内経済の成長を図っていく通常の産業政策としてはよく出来ていると評価いたしますが、
山本県政が推進する産業政策は、その域に留まるものであってはなりません。
そこで第一点のお尋ねです。山本知事が目指すモデル地域としての山口県を実現するという観点からの産業政策についてどうお考えなのか、ご所見をお伺いいたします。
第二点は、食品産業の基幹産業化についてであります。
先日、今月の11日ですが、フランス料理の世界的巨匠で「厨房のピカソ」と呼ばれるピエール・ガニェール氏が山口県庁を訪れ、 山本知事より「美食王国やまぐち親善大使」の委嘱状を受け取りました。ガニェールさんは、フレンチシェフとして三つ星を獲得、 日頃から山口県産アマダイを使うなど、山口の食材に関心を示していたため、県が美食親善大使就任を打診していました。
ガニェールさんは委嘱式で、「山口県の食材にはたくさんすばらしいものがある」と県産の魚や牛肉、ウニ、野菜などを高く評価。 山本知事は「世界的水準にある山口県の食材を、彼の目で評価し紹介して頂ける点を心強く思っている」と話した、と新聞は報じております。
ガニェールさんは、来年3月に県産食材と萩焼を融合させた創作料理を発表する予定だそうです。こうした企画により、食の面で山口県のイメージが高まり観光力のアップに繋がることが期待されますが、
それ以上に私が注目するのは、ガニェール氏の美食親善大使就任と、本県食材への評価は、山口県の食品産業が世界市場をマーケットとする基幹産業になり得る可能性を示唆するものではないかということであります。
私は、ガニェール氏の「美食王国やまぐち親善大使」就任を着想し実現した関係職員の努力を高く評価するものでありますが、この企画実現を一過性に終わらせることなく、 将来を見据えて本県の食品産業を基幹産業に育てる可能性を切り拓くことにつなげていってほしいと思う次第です。
三方海に開かれ、海幸、山幸の食材豊かな山口県は、食と健康と知が集積したフードバレーを形成するにふさわしい県であるということを、 私は、これまで議会で度々提唱して来ましたが、そのことは食品産業を基幹産業に育てていくという取り組みの中で、自ずと形成されるものであり、
その方向は、山本知事が目指す地域モデルである農林漁業と工業、商業がバランスよく発展し共生する社会の実現に繋がるものであります。
「やまぐち産業戦略推進計画(中間案)」は、重点戦略の柱の一つに、「地域が輝く『農林水産業活力向上戦略』」を掲げ、県産農林水産物のブランド化による魅力の向上や、
アジアへの輸出拡大に取り組むこととしておりますが、こうした戦略目標は、県の食品産業を基幹産業に育てていくという政策目標を明確にして推進することによって達成されるものと考えます。
県の基幹産業は、県域を越えた市場をマーケットとする産業ということですが、グローバル経済の今日、それは当然に世界市場をマーケットとする産業であり、従って輸出産業であります。
私は、本県の食品産業はそういう意味での基幹産業として世界市場をマーケットとする輸出産業を目指すべきであり、そう成り得る可能性を有していると見ている次第でありまして、
この度の産業戦略中間案が、プロジェクト事業としてアジアに向けた県産農林水産物の輸出拡大に取り組もうとしていることを支持するものであります。
ただ農産物の輸出ということでは、私は、数年前この議会で県産米の台湾輸出が実現したことを高く評価し、さらに中国へのコメ輸出に取り組むことを提案したことがあります。 しかし、現在はその考えが変わりました。それは、食料の輸出で主力とすべきは、農産物そのもの、海産物そのものではなく、それを加工した食品であるということに思いが至ったからであります。
農産物、海産物そのものの輸出は、どうしても高価、高品質のものに限られ、供給対象も主に富裕層で、需要、供給いずれの側にも裾野の広がりが期待できません。
一方、加工食品は、どういう付加価値をつけるかであらゆる階層が供給対象となり、需要、供給いずれにおいても裾野の広がりには限りがありません。
そこでお尋ねです。私は、以上申し上げましたことから、本県の食品産業を世界市場をマーケットとする基幹産業に育てていくべきだと考えますが、 このことにつきご所見をお伺いいたします。また、そのことを推進するため、食品加工研究体制の充実が必要と考えますが、このことにつき併せお伺いいたします。
|
| |
上関町の産業力・観光力強化支援について |
| |
「座して待つ訳にはいかない。」、上関町の今日の思いを一言で表現すれば、そういうことだと思われます。
上関町は、上関原発の建設計画が中止になった場合、町の振興と住民への行政サービスの確保を如何にして図っていくかの課題に現在真剣に取り組んでいます。
勿論、原発誘致による町興しの基本方針は変わっていません。しかし、福島原発事故以後、国民世論の大勢が「原発依存を減らす。」という方向になっている中において、
我が町の繁栄のためにということで原発建設を声高に求めることはしてはならないと自制しています。そして、原子力発電所が立地されない場合を想定して、
原発関連の財源収入がないという状況のもとで、町の財政運営をどうしていくのか課題に取り組んでいる訳です。
国がエネルギー計画において上関原発建設の方針を明確にすればそれに協力する姿勢を堅持する。しかし、上関原発が立地されなくなった場合は、それはそれとして受け入れ対応していく、
上関町はそう腹を固めております。よって、一番困るのは、上関原発が建設なのか中止なのか定まらないまま中途半端な状態が続き、将来に向けて町の展望を描けないことであります。
ところが、現在の国のエネルギー計画策定に向けての動きを見ていますと、上関原発を含む11基の新設・増設の原発の建設計画がどうなるのかの判断は、随分先になるように思われます。
年内に策定予定の国のエネルギー基本計画においても、大局的、中長期的な観点から方向性を示す内容に留まり、電源構成をどうしていくかを具体的に示すものとはならない見通しであります。
現在、国の原子力政策における最大の関心事は、既存の原発の再稼働であります。この再稼働を認めるかどうかの審査は、原子力規制委員会が行ないますが、この規制委員会は、
三つの審査チームを設け、今年7月に策定予定の新しい安全基準に基づき一つの原発を約半年かけて審査する方針です。従って、既存の原発は50基あることから、順調にいっても全ての既存の
原発について審査が完了するまでには、8年以上かかる計算になります。
また現在、政権党である自民党は、「10年以内に、電源構成のベストミックスを確立する。」と公約しています。電源構成のベストミックスをどうするかについての最大の焦点は、
総発電量における原子力発電の割合をどうするかということであります。
こうしたことから、上関原発を含め新規の原発建設計画をどうするかについて国の考えが定まるまでには、この電源構成のベストミックスと既存原発の再稼働についてその全体像が
具体的に見えてくることが必要との観点に立てば、今後10年近く要することになります。
しかも、国のエネルギー政策が、原発ゼロではなくても「原発依存を減らす」という方向に進むのであれば、原発の新規計画の中でも増設ではなく純然たる新設であり、
未だ準備工事段階であって正式な建設許可が下りていない上関原発は、計画中止になる公算が高いと常識的には思われます。
その間、「座して待っている訳にはいかない。」、上関町がそう考えるのは、当然のことであります。
私は福島原発事故以後、上関原発の建設計画は中止すべきとの立場を明確にしてきましたが、原発による町興しを上関町が政策として選択して来た所以は理解する必要があると考え、
上関町の現状や歩みを知る努力をしてきました。
そして、記紀万葉の古代から、瀬戸内海の海上交通の要衝として栄えてきた歴史があること。それが、船が帆船の時代から動力機関を備えた船舶の時代に移行すると共に、
主に潮待ちの港としての上関の役割が薄れていったこと、それでも明治時代から終戦後頃までは人口が一万人ほどであったのが、戦後の復興、高度経済成長、
都市化の進展の中で上関町では人口流出、過疎化が続き現在は人口が、3千数百人にまで減少していること、町のほとんどが山地であり平地が少なく、以前は水道もなく産業振興、
企業誘致の有効な策がなかなか見いだせなかったことから、原発誘致で活路を切り拓こうと町を挙げて取り組むことになったこと等のことがわかってまいりました。
それが、3.11福島原発事故以後、原発立地が不透明となり、それがない場合を想定した町振興の課題に取り組まざるを得なくなりました。このことは、私は上関町にとっては幸いであったと見ております。
確かに、原発誘致は数十年の賑わいをもたらしてくれるかもしれません。しかし、原子炉の寿命は原則40年とされており、その後は高レベル放射性廃棄物としての廃炉が残ります。
さらに、使用済み核燃料も核燃料サイクル確立の見通しが立っていないことから、原子炉に併設される核燃料プールに保管されたままになる可能性が高いと思われます。
福島原発事故で、最も憂慮されたことの一つは、4号機の燃料プールが余震や水素爆発で崩壊したり、若しくはプールの水が蒸発してなくなってしまい、
そこに保管されている核燃料が露出してしまうことでした。そうなった場合は、首都圏を含めた3000万人避難という最悪事態も想定されていました。
使用済み核燃料が安全な状態になるまでには少なくとも10万年は要すると見られており、その間の安全管理をどうしていくかの解決策は、未だ確立されていません。
原発立地は、そうしたものを併せ抱え込んでしまいます。
上関は、記紀万葉の時代のみならず、遺跡からすると縄文時代にさかのぼって住民の生活があった地域であることがうかがえ、これからもまた、
数千年以上にわたって人々の暮らしが営まれる地域であることを思えば、出来れば困難な道であっても原発立地に頼らず町の振興を図っていくことが、
上関町にとって望ましいことのように、私には思われます。
ただ上関町は、国のエネルギー計画に上関原発の新規立地が位置づけられない可能性もあることから、その場合に備えての検討を真剣に行った次第で、
検討会においては、原子力発電所の是非については一切議論されていません。
私は、上関町のこのような今日の事態への対応姿勢は、誠に的確であると思うものでして、その結果、原発立地如何にかかわらず、上関町の地域資源を生かす施策を、
ハード・ソフト両面から推進することが、町政運営の中軸となりつつあることを評価するものであります。そして、そうした上関町の取り組みを県も支援すべきであると考え、
「上関町の産業力・観光力強化について」ということで、端的に以下三点お伺いいたします。
第一点は、財政支援についてであります。
今後、上関町への原発関連の交付金が、どれだけ確保されるか不透明な中、少なくとも向こう10年にわたって上関町が、今日の行政水準を維持し、
将来に向かって町の振興のために政策投資が出来るよう県も必要に応じて財政支援をすべきであると考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。
第二点は、観光力強化への支援についてであります。
上関町のキャッチフレーズは、「花咲く海の町」ですが、上関町は加えて歴史の町であり、様々なストーリイの観光ルートの設定が可能であります。
また、かって昭和40年代、NHKの朝の連続ドラマ「鳩子の海」や、山田洋次監督の映画「愛の讃歌」の舞台になったこともあり、観光面での潜在的ポテンシャルは大きいと思われ、これを最大限生かしていくことが町振興の重要な柱の一つであります。
そこでお尋ねです。山本県政が全力を挙げて取り組む最優先課題の一つが観光力の強化でありますが、上関町を含む広域観光ルートの開発を図るなど、上関町の観光力の強化について、どう支援していかれるのか、ご所見をお伺いいたします。
第三点は、漁業の6次産業化への支援についてであります。
上関大橋の室津側のたもとに整備される「ふるさと市場(仮称)」は、来年秋オープン予定であります。ここでは、上関の海産物をはじめとする特産品が展示販売されますが、その中には勿論祝島の海産物、特産品もあります。
この「ふるさと市場」を、しっかりしたものにしていこうという点では、原発への賛成、反対は関係ありません。私は、素晴らしいことだと思います。
上関町で基幹産業に育つ可能性がある産業分野と言えば、やはり漁業ということになると思いますが、そのためには加工・流通のみならず観光も含めた漁業の6次産業化への取り組みが不可欠であり、
「ふるさと市場」の開設は、そのことに大きく寄与するものと期待されています。
また上関は、海産物の加工という点では、「平天が、うまい。」ということはよく知られており、私も上関に入ったら必ず平天を買って帰りますが、
こうした製品が、「ふるさと市場」の開設で、より広く知られることになり、さらには新たな製品が次々と開発される契機になることが期待されます。
そこでお尋ねです。上関町において漁業を基幹産業に育てていくためには、観光を含む漁業の6次産業化を進めていくことが不可欠であり、
「ふるさと市場」の開設は、このことに大きく寄与するものと期待されています。ついては、こうした取り組みに対し、県もしっかりした支援をしていくべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
|
| |
|
|
|
| |
○9月定例県議会 |
| |
7月28日大雨災害について |
| |
「災害は忘れたころにやってくる。」と云いますが、本県はここ5年の間に、平成21年、22年そして今年と、忘れる間もなく三度大雨災害に見舞われました。
平成21年7月21日の豪雨災害では、主に防府・山口地域で土砂災害、浸水被害が発生し、17名の方が犠牲となられ、損壊・浸水被害を受けた家屋の総数は4698棟に上りました。
その一年後、平成22年7月15日の大雨災害では、県西部を中心に、局地的な集中豪雨に見舞われ、厚狭川や木屋川の氾濫等により、多数の家屋の浸水や道路交通網寸断等の被害が生じました。
そして、今年の7月28日大雨災害。気象庁が「これまでに経験のない大雨」と警戒を呼び掛けた猛烈な大雨に見舞われ、山口市の阿東地域、萩市の田万川・須佐地域、阿武町等において河川の氾濫、土砂災害等が発生し、2人の方が亡くなられ1人の方が行方不明となりました。また、山口市の市街地及びその周辺地域においては内水による浸水被害が生じました。
そこで、今回は「7月28日大雨災害について」ということで、過去の大雨災害も踏まえ、今回の災害からの復旧と、内水浸水被害対策についてお伺いいたします。
(1) 河川の復旧について
先ず、お尋ねの第一は、「河川の復旧について」であります。ご案内の通り、7月28日早朝からの猛烈な雨は、1時間の降水量が、山口市では143.0ミリ、萩市須佐では138.5ミリと、いずれも「これまで経験のない」観測史上最大の大雨となりました。
このため、阿武川、田万川、須佐川等の水系において河川が氾濫し、流域に甚大な浸水被害が発生しました。
県は、先の8月臨時県議会において、「このたびの集中豪雨も踏まえた河川整備のあり方について速やかに検討したい。」「局地的な集中豪雨はいつでもどこでも発生するといった観点から、このたびの集中豪雨を主要水系に再現し、各水系における洪水の発生状況等を検証する。」「この度の集中豪雨も前提とすべき気象条件の一つとして整理した上で、総合的な治水対策を効率的、効果的に進める。」旨、表明しておられます。
そこで、特に阿武川、田万川、須佐川の三水系の河川復旧について、2点お伺いいたします。
第一点は、阿武川、田万川、須佐川の三水系の復旧方針についてです。この三水系の復旧は、当然に先の8月臨時議会で示された河川整備、治水対策の方針に基づいて行なわれ、将来今回同様の大雨が降ったとしても流水の氾濫を生じない河川となるよう改良整備されるものと考えておりますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。
第二点は、特に阿武川の鍋倉地域の改良整備についてであります。阿武川は、鍋倉のリンゴ園の手前のところで右に大きく蛇行しております。その蛇行し始めのとこらから左岸側数十メートルは、護岸強化の工事が10年程前に行なわれています。これは、水害対策としての河川改良工事の一環であったと思われますが、この度の大雨で増水した流水は、
その護岸を越水してリンゴ園が冠水する事態となりました。また、蛇行前の左岸側は護岸の強化がなされていないために、増水した激流が大量に越流して鍋倉のリンゴ園一帯に流れ込み甚大な被害を生じました。ここで長年リンゴ園を営んでおられる園主の方は、過去これまで昭和38年と47年の二度被災しており、今度で3度目です。もう二度とこういうことが起こらないようしてほしいと、繰り返し訴えておられました。
当然の思いで、河川の復旧改良は、それに応えるものでなければならないと考えますが、過去に浸水被害があった時には、抜本的対策として河川の線形を変えて蛇行そのものを無くす河川改良も検討されたように聞いております。
そこでお尋ねです。阿武川の鍋倉地域において再び浸水被害を生じないようにするためには、抜本的な河川改良が必要と考えますが、どのように整備される方針なのか、ご所見をお伺いいたします。
(2) 内水浸水被害対策について
水害といえば、従来河川の氾濫による浸水被害のことでありましたが、近年は、河川の氾濫というより河川に雨水が排水されないための浸水被害、所謂内水浸水被害が頻発するようになり、これの解消が暮らしの安全・安心を確保する治水上の新たな政策課題となって来ております。
この度の大雨災害においても、山口市北部の市街地及びその周辺地域では、629戸の内水浸水被害が生じており、そのうち105戸は床上浸水でした。この地域は、椹野川水系の流域でして平成21年7月の豪雨災害時にも、1400戸ほどの浸水被害が生じておりまして、
そのほとんどは内水浸水被害でした。この5年の間に二度床上浸水に見舞われた家屋も数多くあり、浸水被害が生じないように抜本的対策を求める声は、切実なものがあります。
山口市において、平成21年そして今年と二度も内水浸水被害が大量に生じた背景を調べますと、頻発する記録的な大雨に、雨水排水の下水路及びこれを最終的に受け入れる河川が、対応しきれていない実情が見えてきます。
先ず、雨水排水の下水路について申しますと、山口市は国の指針に基づき県が示した確率年10年の時間降雨55mmに対応する水準で、雨水排水の下水路整備を行ってきております。ところが、10年に1回の確率で発生すると見做されている時間雨量55mmを大幅に超える降雨が、
この10年の間に6回も発生しており、雨水排水のための下水路整備の水準は現行のままでいいのか、その妥当性が問われています。
さらに問題なのは、雨水排水の整備水準を見直して、雨水下水路の排水容量を拡大したとしても、河川がその下水路を通して排水された雨水を受け入れることができなければ、雨水は下水路から溢れて内水浸水被害が生じるということであります。
現に、今年の夏の大雨で山口市の湯田地区、吉敷地区は併せて340戸の浸水被害が生じ、その内85戸は床上浸水でしたが、それは被害地域の雨水排水路が接続されている椹野川の支流である県河川前田川が、増水して水位が高くなり雨水の受け入れができなくなったためでした。
このことから明らかになって来るのは、内水浸水被害を無くするためには、下水路だけではなく河川の整備も併せて一体的に取り組まなければ抜本的な解決にならないということであります。そのためには、雨水の排水路を整備する下水道事業は市町の事業であり、
市町が整備した下水路の雨水は、ほとんどが県河川へ排水されることから、県と市町が連携し一体的に内水浸水被害対策には取り組む必要があることを強く訴えたいと思います。
そこで、これからは県も内水浸水被害を解消するという治水上の政策課題を市町と共有して、県河川の整備を行っていくべきであり、県の河川整備の方針及び計画は、そういった問題意識、課題意識に立ったものにすべきだと考えます。
県は、現在主要河川については、河川整備の長期的将来像を示す河川整備基本方針と当面する20年ないし30年間に行う整備事業と達成すべき整備水準を具体的に示した河川整備計画を策定して河川整備を進めていますが、
こうした現行の河川整備基本方針および河川整備計画は、内水浸水被害の解消という視点からも、その妥当性を点検する必要があるのではないでしょうか。
県は、平成21年、22年の豪雨災害を受けて、平成22年8月に「局地的な集中豪雨に対応した治水対策検討委員会」を設置しました。この検討委員会は、翌年の平成23年8月に、
検討結果を提言書としてまとめ報告しております。それによりますと検討委は、県下主要10河川について、現行の河川整備基本方針や河川整備計画を検証して、河川整備基本方針については10河川全て妥当とし、
河川整備計画については椹野川を含む6河川の現行計画は、妥当である旨の判断を示しています。
はっきり言ってこの検討委の提言書は、河川の氾濫、洪水という外水による浸水被害の発生を予防し、軽減するという視点からのものであって、内水による浸水被害への対応という視点が欠けています。
そういう検討結果になった理由が、もし内水浸水被害は市町が行なう下水道事業において対応すべきものであって、県の責任範囲ではないとの考えによるものであるとしたら、そういう考えは改めなければなりません。
確かに、内水処理は下水道事業として対策が講じられるべき市町の事業であります。そして、それは単に雨水排水の下水路の整備のみならず、排水ポンプの設置あるいは雨水の流出抑制を図る調整池や浸透マス等の雨水貯留・
浸透施設の整備なども含めて計画整備されるべき事業であります。
しかし、そうした内水処理の事業も、水系一貫して下水道計画と河川の改修計画との整合が十分図られた上で取り組まれてこそ、浸水被害が生じないように真に治水の実をあげることができるのです。そういう意味において、
内水浸水被害の解消は、市町のみならず県にとっても治水上の政策課題であることを、改めて指摘しておきたいと思います。
国土交通省も近年、河川と下水道とが体系化された総合的な雨水排水計画を策定することが、双方が一体となって地域の治水安全度の向上を図ることになり、都市部における雨水対策事業の効率的な推進が図れるということで、
総合的な都市雨水対策の策定およびそのための協議会の設置を促し、推進しております。平成23年7月末時点での、全国における協議会の設置及び計画の策定状況は、配布の参考資料の通りであります。
気象庁は、頻発する局地的な集中豪雨は、今後増えることはあっても減ることはなく、強くなる旨の見解を明らかにしており、今日このことに対応した内水も含めての総合的な治水対策が求められています。
以上申し上げましたことを踏まえ、以下4点お伺いいたします。
先ず第一点、内水浸水被害の解消を、県の治水への取り組みにおいて市町と連携し解決すべき重要な政策課題として位置づけるべきであると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
次に第二点、河川の復旧についての質問の時に触れましたが、県は8月臨時議会において、「この度の集中豪雨も踏まえた河川整備のあり方について速やかに検討したい。」
「この度の集中豪雨も前提とすべき気象条件の一つとして整理した上で、総合的な治水対策を効率的、効果的に進める。」旨、表明しておられます。そこでお尋ねですが、ここで言われている
「河川整備のあり方の検討」には内水浸水被害解消の視点を、そして「総合的な治水対策」には、内水浸水被害対策を含めるべきであると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
第三点、椹野川水系のように、大雨のたびに内水浸水被害が数多く発生しているところにおいては、県と市が一体となって河川と下水道が体系化された総合的な雨水排水計画を策定することが必要であり、
そのための県市合同の協議会を設置すべきであると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
第四点、内水浸水被害が生じている流域における当面の緊急対策としては、関係する県河川の浚渫をしっかり行ない、大雨時の増水による水位上昇の抑制を図る必要があると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
(3) 被災地の復興について
被災地の復興については、要望とさせていただきます。
この度の大雨災害で被災地になったところは、もともと過疎化、高齢化が進んでいた地域であります。よって、たとえ災害からの復旧がなされたとしても、その傾向が一層進むのではないかと懸念されています。
そこで、そういうことにならないよう、むしろこの度の災害を、「禍を転じて福と為す」契機にすることができるよう、被災地の復旧後の新たな地域づくり、そういう意味での復興への取り組みを、県もしっかり支援されますよう強く要望いたします。
|
| |
山口県立大学の定款変更について |
| |
今議会に提案されています山口県立大学の定款を変更する議案について、四点お尋ねいたします。
先ず第一点は、定款変更の理由についてであります。
地方独立行政法人法は、「公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。」と定め、「ただし、定款で定めるところにより、学長を理事長と別に任命することができる。」としております。この制定趣旨は、公立大学法人においては、本来理事長が学長になるのが原則であり、設立団体の意向により、別置も可能とする、というものだと思われます。
そこで、山口県立大学を独立行政法人化する時は、準備委員会で学長と理事長を一体型にするのか、別置型で行くのかの議論が行なわれまして、大学の規模や歴史からして一体型が望ましいとの考えが大方の意見となり、その旨が定款に定められました。
県立大学より規模が数倍も大きい国立大学は、基本的に理事長・学長一体型であります。また、都道府県立の公立大学が法人化した公立大学法人においては、全国41の公立大学法人のうち29大学が一体型であり、12大学が分離型であり、3分の2強が一体型でありまして、私は準備委員会で集約された意見は妥当なものであったと見ております。
法人化された県立大は、江里新理事長が学長も兼ね、様々な大学改革を実現してきました。そこに何の支障もなかったように思われます。それを、この度敢えて理事長と学長一体型を、理事長と学長別置型に変更しようとする理由は何なのか、ご所見をお伺いいたします。
第二点は、定款変更について県の考えが、大学側に伝えられた時期についてであります。
県から大学法人に、「運営体制変更」についての協力要請文書が発出されたのは、今年の8月2日です。県の定款変更の意向が文書で正式に大学側に伝えられたのは、大学が夏休み期間に入ろうとしていて、大学の先生方はお盆を挟んで、色々と行事予定を組んでいたであろう8月になってからのことでした。
定款変更について、大学側の議論や意見集約を重視する姿勢があれば、5月初旬には、県の考えを伝えるべきであったと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
第三点は、第二点の質問と関連しますが、大学内の議論と意見集約が不十分ということです。
県立大学定款変更は、大学法人の審議機関である教育研究評議会と経営審議会の議を経て、「新たな運営体制への円滑な移行に向けて協力する。」との大学法人からの回答を受けて、今議会に議案が提案されています。
定款変更のことが、大学の各学部長や研究科長等で構成される教育研究評議会に諮られたのが8月6日で、第2回目の8月26日の評議会において「新たな運営体制への円滑な移行に協力する。」との審議結果になったとされています。
大学の経営審議会に諮られたのは、8月29日で、同様の審議結果になったとのことであります。
ここで指摘しておかねばならないことは、山口県立大学が定款に定めている仕組みが、まさしく課題への対応を迅速・的確に行うことができるよう、また機能性・機動性ある大学運営ができるよう、
理事長である学長に権限を集中しているということであります。従って、大学法人の審議機関である教育研究評議会と経営審議会の構成員は、基本的に理事長の指名もしくは任命による選任になっております。
よって、理事長が強い意思で臨めば、両機関とも色々意見があっても最終的には審議結果が、理事長の意向に沿ったものになることは想像に難くありません。この度の定款変更に向けた経緯は、 手続き的には何ら瑕疵がないように思われますが、事実の経過を仔細に点検していきますと、大学内における議論、意見集約が十分であったか疑問です。
そこでお尋ねです。特に大学の在り方の根幹にかかわる今回のような定款変更の事案は、県と大学双方における合意形成に向けた丁寧な議論と意見集約のプロセスが確保されるべきところ、
それが決定的に欠けていたように思われますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。
第四点は、理事長の任期についてであります。
地方独立行政法人法では、第74条において、「公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規定で定めるものとする。」
と、しております。これを受けて山口県立大学は、学長となる理事長の任期は、一期目4年とし、再選は可能で二期目の任期は2年で、最長6年間となっております。こうした定めは、学長になる理事長に権限を集中して、
様々な大学の課題に理事長が対応しやすくする一方、大きな権限を持つ地位に同一人物が長くいることによる弊害を避けようとの考えに基づくものだと見ております。
それが、今回提案されている定款変更が成立して学長と理事長は別置型となった場合、理事長は知事の任命となり、理事長の任期は4年とするも再任されることができるとなっていて、任期最長6年の制限はなくなります。
よって、現在の理事長は、県大が法人化されたとき最初の2年間特例で理事長を務めたことがあり理事長在職8年目ですが、その現理事長を任命することも可能になります。
そこでお尋ねいたします。県立大の定款変更の議案が成立した場合、新たな理事長は知事任命となりますが、知事は、理事長の任期についてどうお考えなのか、ご所見をお伺いいたします。
|
| |
|
|
|
| |
○11月定例県議会 |
| |
観光力の増強について |
| |
「秋吉台の地質構造を知ることは、日本列島の生い立ちを知ることになる。」、秋吉台科学博物館発行の「秋吉台3億年」には、こう記されています。
美しい広大なカルスト台地である秋吉台は、その地下に秋芳洞をはじめとする450もの鍾乳洞を蔵しており、学術的価値の高い自然の景勝地として、山口県を代表する観光地になっております。
山口県観光客動態調査によれば、昨年平成24年の県外からの観光客数第一位の観光地は秋吉台・秋芳洞で、694,884人県外から訪れています。以下県外からの観光客数ベストファイブをご参考までに紹介いたしますと、
第二位が岩国市の錦帯橋で649,062人、第三位がしものせき水族館「海響館」で470,884人、第四位が山口市の瑠璃光寺五重塔があります香山公園で466,791人、第五位が萩の松陰神社で450,704人となっております。
次に、インバウンド即ち海外からの観光客の動態を市町別に見れば、県内ビッグスリーは岩国市、山口市、美祢市でして、平成24年は美祢市が第一位で24,988人の外国人観光客が美祢市に訪れています。
その殆どは、秋吉台・秋芳洞を観光したであろうことは想像に難くありません。
このように秋吉台・秋芳洞が、今日も本県を代表する観光地であることに変わりはありませんが、かって年間200万人もの観光客が訪れて賑わっていた当時と較べると、現状はいささかさびしい感がいたします。
この景勝に優れ、学術的価値の高い秋吉台・秋芳洞に、かっての賑わいを回復することができれば、美祢市のみならず近隣の山口市、長門市、萩市、下関市、宇部市、ひいては岩国市を含む全県の観光力アップ、
経済活性化に繋がると見ております。県内で最も離れている岩国市との関連では、昨年12月に開港した岩国錦帯橋空港の復路の利用者の1割強は目的地が美祢市であり、秋吉台、秋芳洞等への観光客であることがうかがわれます。
県が今年の10月に策定した「やまぐち観光推進計画」を見ますと、本県観光の課題として「観光ポイントが分散」していることを指摘していますが、観光地としての評価、実績においても、
地理的位置が県内各地の観光地と観光ルートを組み合わせやすい点においても、秋吉台・秋芳洞を県内観光の核となるポイントとして育てていくことが、山口県全体の観光力増強に繋がるのではないでしょうか。
そこで、本県の観光力増強に向けてのお尋ねの第一点は、山口県観光の核となるポイントに、秋吉台・秋芳洞を位置づけることについてであります。
秋吉台・秋芳洞は、全国的に知名度があり誘客力ある本県を代表する観光地であります。私は、その秋吉台・秋芳洞への特に県外からの観光客が増えることは、県内各地の観光地が潤うことに繋がると見ております。
県外から秋吉台・秋芳洞の観光に来た人たちは、必ず他の県内観光地をセットで観光すると思われますし、宿泊は美祢市は受け入れ能力が小さいので、
大方は周辺の長門市の湯本温泉や山口市の湯田温泉あるいは萩市等になるであろうと思われまして、秋吉台・秋芳洞と県内観光地はウィン・ウィンの関係にあるからです。
ついては、秋吉台・秋芳洞を県観光の核となるポイントとして位置づけ、時代のニーズに応じた観光地としてのリニューアルとブラッシュアップに取り組むことを、県の観光力増強に向けた戦略の柱の一つにすべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
次に第二点は、ジオパークへの取り組みについてであります。
ご案内のように、美祢市が世界ジオパーク認定に向けて取り組んでいます。
ジオパークとは、「地球科学的に見て重要な自然の遺産を含む、自然に親しむための公園。地球科学的に見て重要な特徴を複数有するだけではなく、その他の自然遺産や文化遺産を有する地域が、
それらの様々な遺産を有機的に結びつけて保全や教育、ツーリズムに利用しながら地域の持続的な経済発展を目指す仕組み」とされています。ジオパークのジオはギリシャ語で、土地、地理、地球などを表す言葉です。
ジオパークには日本ジオパークと世界ジオパークと二通りあり、先ず日本ジオパークの認定を経て世界ジオパークの認定を目指すことになります。日本国内におけるジオパークの評価や認定は日本ジオパーク委員会が行い、
この委員会が、日本ジオパークの認定を受けた地域の中から世界ジオパークの候補を推薦することとなっております。現在、日本国内において世界ジオパークの認定を受けた地域は、京都府・兵庫県・鳥取県の山陰海岸や島根県の隠岐など6地域、
日本ジオパークの認定を受けた地域は、伊豆半島、佐渡、阿蘇など32地域となっております。
美祢市においては、「世界遺産への登録を。」という声もあったようですが、世界遺産とジオパーク双方について議論検討をした結果、世界ジオパーク認定を目指すこととし、平成22年度に策定した「美祢市総合観光振興計画」に、そのことを重点プロジェクトとして掲げました。
その後、平成23年4月に市役所内にジオパーク推進室を設置、翌平成24年3月には、21団体で構成される「美祢市ジオパーク推進協議会」を設立、
この協議会には山口県も宇部県民局長を構成メンバーとする形で参加しております。そして、今年平成25年4月に、日本ジオパークネットワークに加盟申請書を提出、
審査結果は9月に開催された日本ジオパーク委員会において発表されましたが、「拠点施設、パンフレット、解説板等のジオパークを認識できる整備は進んでいない」等との理由で認定は見送りとなりました。
私は、美祢市が世界遺産登録ではなく世界ジオパーク認定を目指すことにされたことを、妥当な判断として評価するものです。美しいカルスト地形を造り、
その地下に秋芳洞をはじめとする巨大な鍾乳洞を育んだ秋吉台は、地球の歴史の中で自然が造りあげた大傑作であり、冒頭紹介しましたように日本列島の生い立ちを知るうえでの貴重な地質構造を、
今日に残している学術的価値が高い自然の景勝地であります。そうした秋吉台・秋芳洞をはじめとする地域の様々な大地の恵みと特質の広がりを、地道ではあっても時の経過とともに着実にブラッシュアップしていく方向として、
世界遺産よりジオパークの方がふさわしい、私は、そう理解しております。
今回は、美祢ジオパークの日本認定は見送りとなりましたが、この地域のジオパークとしての潜在的価値は卓越したものがあり、必ず近い将来、日本ジオパークの認定、そして世界ジオパークの認定に至るものと確信しております。
そして、そのことは結果的に秋吉台・秋芳洞をはじめとするこの地域の観光的価値もさらに高めることになり、ひいては本県観光の底上げにも資することになると思われます。
このような美祢市のジオパーク認定に向けての取り組みに対して、県はこれまで推進協議会の構成メンバーになり、支援の姿勢は取っていたものの、基本的には見守るスタンスではなかったでしょうか。
私は、美祢市のジオパーク認定に向けての取り組みは、県全体の観光力増強にもつながることを認識し、県も支援の姿勢から更に一歩踏み込み、美祢市と共に取り組むということにすべきだと考えます。
そこでお尋ねです。ジオパークの認定は、ジオパークとしての活動や事業がどういうものかということが問われ、そのためのハード、ソフト両面での整備が充分かどうかが審査されることになると思われます。
そうしたジオパークとしてのハード、ソフト両面での整備に、県も美祢市と共に取り組み、必要な役割を担うべきだと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
観光力増強に向けてのお尋ねの第三点は、修学旅行についてであります。
明治維新に始まる近代日本の成り立ちを知る上において、また日本列島の生い立ちを知る上において山口県は恰好な県であります。明治維新に関する史跡は、萩市をはじめ県下各地に豊富にありますし、
自然が3億年にわたって造り上げた秋吉台からは、地球の歴史そして日本列島の生い立ちを学ぶことができます。従って、中学校・高校において特別活動として学校教育の一環に位置付けられている修学旅行の行き先として、
山口県は最も相応しい県の一つだと思われますが、実際はそうなっていません。
財団法人日本修学旅行協会が、平成23年度に実施された中学校の修学旅行に関して実態調査を行っておりますが、それによりますと、都道府県別旅行先順位は、
山口県は第18位で、構成比は0.6%であります。因みに、第1位は京都府で構成比は20.7%、第2位は奈良県で構成比は16.3%です。高校については、平成22年度の修学旅行に関して調査し、
見学先上位20位迄を公表しておりますが、そこには山口県の観光地は一つもなく、また、県の観光客動態調査でもそうした実態は十分に明らかにされていません。高校の修学旅行で特徴的なのは、
見学先上位10位迄に、首里城やひめゆりの塔など沖縄の見学地が6カ所含まれていることです。平和教育と今日主流になりつつある体験学習を含んだ修学旅行の適地として沖縄が選ばれるケースが多いようです。
中学生、高校生の多くが修学旅行で沖縄に行き、沖縄の自然や風土に触れると同時に、戦争の悲惨さ平和の尊さを学ぶことは意義あることで、それはそれでいいことだと思います。
ただ同様に、全国の中高生に山口県に来て明治維新の史跡に触れ、秋吉台・秋芳洞を訪ねてほしい、そして近代日本を築いた先人たちや日本列島形成に至る壮大な地球のドラマに思いを馳せ、立派な日本人に育つ糧にしてほしいと願う次第です。
明治維新の史跡と言えば、萩の松陰神社に在る松下村塾が代表的ですが、下関の桜山神社招魂場も感銘深いものがあります。維新の戦いに命を捧げた396柱の志士たちの御霊が、
偉大な指導者吉田松陰先生から奇兵隊小者弥吉といった名もない者にいたるまで、同じ墓標で等しく整然と祀られている様は、士農工商の身分制を超えた四民平等の近代日本への理念が、
維新の戦いには息づいていたことを今日に伝えています。また、平和教育ということでは徳山大津島の回天基地があり、日本の代表的な木の名橋である岩国の錦帯橋、大内文化を今日に伝える山口の瑠璃光寺五重塔など、
修学旅行で訪ねれば子供たちが喜び感動するであろうと思われるところが本県には多々あり、最近の修学旅行の概ね6割を占める体験学習型も、新たな人気の産業観光も、優れた魅力的なプランを提供することが可能とみております。
そこでお尋ねです。以上申し上げましたことから、当然に本県の観光力増強に向けた大事な課題として、加えて全国の青少年のための教育的貢献という観点から、
山口県は県観光客動態調査による正確な実態把握に努めた上で、修学旅行の誘致にもっと力を入れて取り組むべきだと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
|
| |
小学校の英語教育について |
| |
「英語は道具であって、人間の価値や人格とは関係ない。」
「小さい時からネイティブ(英語の場合は、英語圏で育ち、正しい英語を話す人を意味する)から英会話を学んだ子たちが、大学では一番下の基礎英語クラスにいる。彼らに共通しているのは、中学一年の時は、英語は楽勝で勉強しなくてもトップだったのが、
二年生後半から英語教育についていけなくなり、極端に苦手になることである。」
「学校教育が目指さなければならないのは、日本人が何よりも日本語を思考の道具として使いこなし、日本人としての資質を身に付けることである。」
「『一流の日本人づくり』が、『国際人づくり』の土台である。日本語での思考の土台が確立され、日本語をしっかり使いこなすことができなければ、どんなに他の言語が技術的にはできても、本当の意味での国際人になることはできない。」
以上は、山口大学で英語を教えておられる先生の論考からの引用です。私は、誠に正鵠を得た大事な指摘であり、今日小学校で進行している英語教育の導入を考える上で参考にすべき卓見であると思っています。
ご案内のように、平成23年度から小学校の5年生、6年生は、「外国語活動」ということで週1時間、年間で35時間、英語学習が行なわれるようになりました。小学校への英語教育の導入は、
平成14年度からで、「総合的な学習の時間」を中心に国際理解教育の一環として英語活動が行なわれるようになったのが始まりです。ただ、このやり方では学校によって内容や時間数にばらつきがあり、
教育の機会均等や中学校に入学した時に共通の基盤が持てるようにということで、小学校5.6年生を対象に英語学習が「外国語活動」として必修化されました。
そして、現在は安倍政権のもと内閣府が所管する教育再生実行会議の第三次提言において、小学校の英語学習の抜本的拡充ということで、実施学年を小学3,4年からにする早期化や指導時間の増加、
更には英語学習を「外国語活動」から正式な「教科」にする等について検討するよう提言されていまして、小学校への英語教育の導入は、一層進む見通しです。
こうした英語教育導入の背景には、アジアの国々が英語教育に積極的だということも影響していると思われます。韓国では1997年に小学3年から、中国では地域の状況に応じて差はあるものの、
基本的には2001年に小学3年から必修化されています。
私は、世界の一体化、そういう意味でのグローバル化が進行している今日、国際的共通語としての英語を学び、身に付け使えるようになることの意義は認めるものであります。ただ、現在導入され、
さらに一層拡充されようとしている小学校の英語教育については、検証が必要と思うことがあり、以下三点ほど、県教育長のご所見をお伺いしたいと思います。
先ずお尋ねの第一点は、現在小学校で行われている英語教育の効果についてであります。平成23年度から必修化された小学校の「外国語活動」は、英語による歌やゲームなどで英語に慣れ親しみ、
英語によるコミュニケーション能力の素地を養うことが目標とされています。意図するところは、そのことが中学校における英語教育の基礎となり、英語の実践的なコミュニケーション能力を培うことに
繋がるということであります。ただ、冒頭に紹介しました山大の英語教育の先生の指摘のように、小さい時からの英会話、コミュニケーション重視の英語学習の効果を疑問視する見方もあり、検証が必要です。
そこでお尋ねです。「総合的な学習の時間」としての英語活動を含めれば小学校への英語教育の導入は10年余経過していることになりますが、そのことは中学校の英語教育に、どういう効果をもたらしていると見ておられるのかお伺いいたします。
お尋ねの第二点は、教育体制についてであります。現在、小学校における英語学習は、学級担任がALT(外国語指導助手)を活用しつつ受け持っているということのようですが、それで中身のある英語学習ができているのか、
英語学習にかかる負担増で学級担任が受け持っている国語や算数などの教科の授業に影響はないのか、英語担当の専科の教諭配置もなされているのか、小学校の教員採用試験においては英語の扱いはどうなっているのかお伺いいたします。
お尋ねの第三点は、国語教育についてであります。2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治先生は、「グローバル化と国際化は連続していますが、区別して考えなければなりません。
国際化は自分たちの国の特質を堅持したうえで、諸外国と関係をつくること。グローバル化は世界の一体化です。」と、述べておられます。正しく至言で、これから日本の特に若い世代に求められる生き方は、
日本人としての特質をしっかり保持した上で、グローバル化に対応していくことではないでしょうか。
従って、グローバル化への対応として英語を道具として使いこなせるようになることは望ましいことでありますが、その土台は立派な日本人であることであり、日本語での思考の土台が確立されていることであります。
そこでお尋ねです。小学校への英語教育の導入により、国語教育がおろそかになるようなことがあってはならない、むしろ国語教育は一層充実されるべきであると考えますが、このことにつきご所見をお伺いいたします。
|
| |
|